育休に入ったとたん、「あれ?思ったよりお金が減ってる…」と焦った経験、ありませんか?
私も1人目のときは「育児休業給付金があるし大丈夫」と思っていました。
でも、実際はボーナスが減り、ベビー用品や税金の支払いなど予想外の出費が重なって、みるみる貯金が減っていったんです。
そのため、2回目の育休では同じ失敗をしないよう、生活費を見直して対策をしました。
2度の経験から、育休中の家計は【我慢の節約】よりも【整える見直し】で大きく変わると実感しました。
この記事では、「育休中の収入減にどう対応するか」「赤字を防ぐ家計の整え方」を体験をもとに紹介します。
今日からできる見直しポイントも具体的に解説しますので、参考になれば嬉しいです。
育休中は収入が減るから生活費が心配・・
育休中の間に家計管理を見直したい
 つばめ
つばめなど、育休中の生活費に不安がある方はぜひ最後まで読んでみてください。
育休中に家計が厳しくなる3つの理由


収入が減る
育児休業給付金の支給を受けられ、元々の収入と比べ67%(はじめの6ヶ月間)や50%(それ以降)の支給があります。
手取りが67~50%まで減ってしまうと思っていましたが、
育休中は社会保険料が引かれないため、想定していたより貰えたという印象でした。



ちなみにつばめは、育休前の手取りが27万円前後で育児休業給付金は20万円ほどいただいていました。
2025年4月からは出生後休業支援給付金制度が新設され、育児休業給付金とあわせて、最大28日間は80%が給付(社会保険料の免除により手取り10割相当となる)が給付されることになりました。
父親は出生後8週間以内、母親は産後休業後8週間以内に、それぞれが通算14日以上の育児休業を取得することが支給条件になります。
しかし、いくら給付金をいただいていても、収入減には変わりありません。
支出が増える(ベビー用品・光熱費・食費)
夫婦共働きの時とは違い、育休中は収入が減るのに何かと支出はかさむ傾向があります。
- ミルクやおむつの定期購入
- 在宅時間増加による光熱費UP
- すぐサイズアウトするベビー服代など・・
育休中は「時間がある=家で過ごす時間が増える」ため、固定費以外にも変動費が増える傾向があります。



育児頑張ってるから、ご褒美のケーキ!疲れたから今日は外食・デリバリー!なども増えがちなんですよねー。
そのため、家計の把握・見直しをしなければ赤字家計になる可能性が高いのです。
想定外の出費(住民税)
育休中でも前年所得に応じた住民税が引かれます。



実際14万円の住民税の納付書が届いた時には驚きました!
普段は給与から天引きされているので、あまり気に留めない部分ですよね。
育休前には、予想外の支出に対応できるように、ある程度のお金の準備が必要だと感じました。
育休中に赤字を防ぐための5つの家計見直し術


「育休中は赤字でも仕方ない」と思っていませんか?
育休中だからこそ取り組める5つのコツで、赤字家計を改善していきましょう。
①固定費を一度リセットする
育休中は外食を減らすなどの変動費よりも、固定費を先に削る方が効果が大きいです。
通信費・保険料・サブスクなど、毎月の固定費を点検。
特に保険は見直しのチャンスです。
今の家族構成に合っていないプランを続けていないか確認してみましょう。
固定費は一度見直せば、節約効果が“自動で積み上がる”のがポイントです。
\ 電気代見直しサイトNo.1 /
②食費の節約術:まとめ買い+冷凍+在庫管理でムダを防ぐ
「育休中は時間がある=節約チャンス」でも、頑張りすぎは続きません。
時短×節約の食費管理術は、こちらの記事で詳しく紹介しています。
また、育休中は寝不足や疲れで食事準備がめんどうになりがちですよね。
レトルト商品、冷凍食品、鍋の素などがあれば簡単に食事を準備することが出来ます。



外食やデリバリーでの散財予防になるためオススメですよ。
\ 自分が住む地域の特売情報をGET /


出典:シュフーチラシアプリのご案内|シュフー Shufoo! チラシ検索
- 無料で使える
- アプリのチラシを見るだけで、ユニクロギフトカードなどが貰えるチャンス



私も、これでスーパーのチラシチェックが一瞬で終わるようになりました!
節約・時短をしたい共働きママは入れておくべきです!
③日用品の節約術:定期便とポイント活用でムリなく節約
おむつやミルク、洗剤など、育休中は「買い忘れ防止+コスパ」を両立するのがポイント。
Amazon定期便・楽天お買い物マラソンなど、ポイント還元率が高いタイミングでまとめ買いしましょう。
赤ちゃんを抱えながら重たい日用品の買い物は大変ですよね。



安くて、家まで届けてくれるネット通販本当に便利ですよ!
④給付金・支援制度をフル活用して家計を支える
育休中に使える給付金や支援制度は、意外とたくさんあります。
代表的なものを押さえておくだけでも、家計の負担はぐっと軽くなります。
- 育児休業給付金:雇用保険に加入している人が対象。育休開始から180日までは給与の約67%、それ以降は50%が支給。
- 出産育児一時金:子ども1人につき50万円(令和5年度以降の額)が健康保険から支給。
- 児童手当:0歳〜中学生までが対象。月1万円〜1万5,000円が支給。
- 医療費助成(自治体):子どもの通院・入院費を一部または全額補助。自治体によって内容が異なる。
- 保育料の軽減・無償化制度:3歳〜5歳は原則無償。0〜2歳でも所得に応じて減額される場合がある。
こうした制度は、自動で支給されるものもあれば申請が必要なものもあります。
「うちは対象かな?」と思ったら、市区町村の公式サイトで早めに確認しておくと安心です。
⑤家計を「見える化」して赤字を防ぐ
育休中は支出のリズムが変わるため、家計簿を一から整えるのがおすすめです。
育休中に家計を整えることで、仕事復帰後も無理なく【貯蓄ができる家計】を維持することが出来ます。
また、【家計を整えるきっかけ】としてFP無料相談を活用するのもおすすめです。
第三者目線で見てもらうと、
“ムダな保険料”や“積立金の見直しポイント”が明確になりますよ。
無料でライフプランの提案、保険の見直し・提案も行ってくれます。



育休中の時間のある間に、プロの力を借りて一度お金の流れを整理しましょう。
\ 無料相談+子育て世帯向けプレゼントあり /
まとめ:育休中は“我慢”ではなく“家計の見直し”で乗り切る


育休中の生活費が足りないのは、珍しいことではありません。
収入が減る時期だからこそ、固定費・変動費・支援制度を整理することが大切になります。
無理な節約ではなく、“仕組みで赤字を防ぐ”ことを意識すれば、心にもゆとりを持って育児に向き合えます。
焦るよりも、今の家計を整えるチャンスと考えて、少しずつ行動していきましょう。
私もそうやって2回目の育休を「不安」から「安心」に変えることができました。



小さな見直しが積み重なって、結果的に**「貯蓄率30%」を維持できる暮らし**に近づきます。
次に読むと役立つ記事はこちら
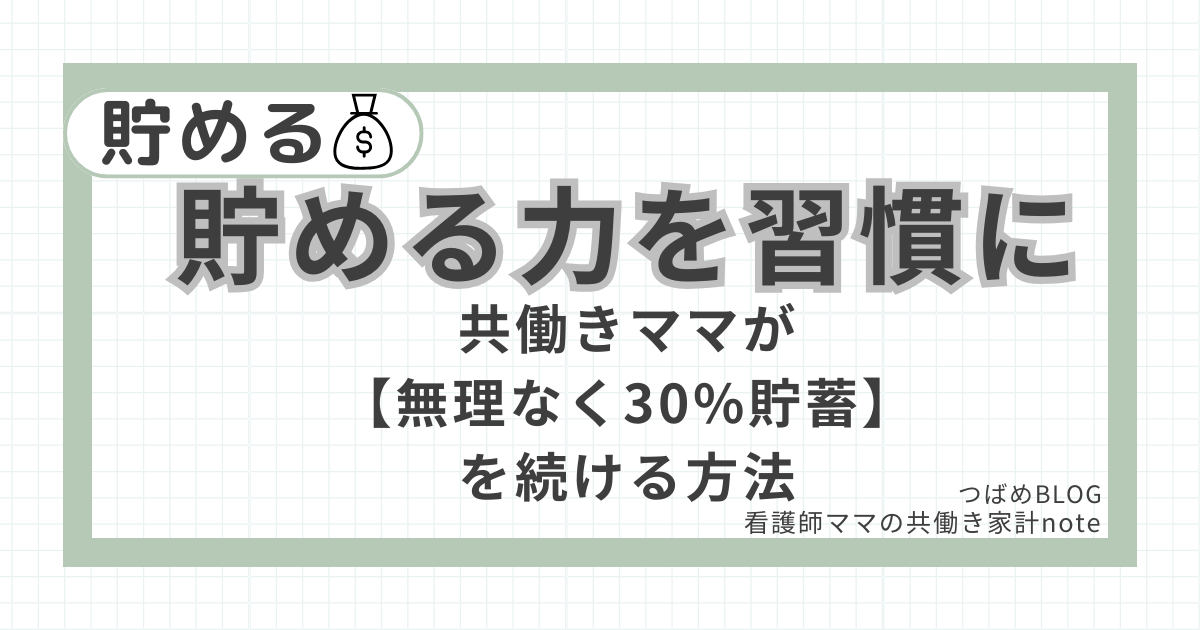
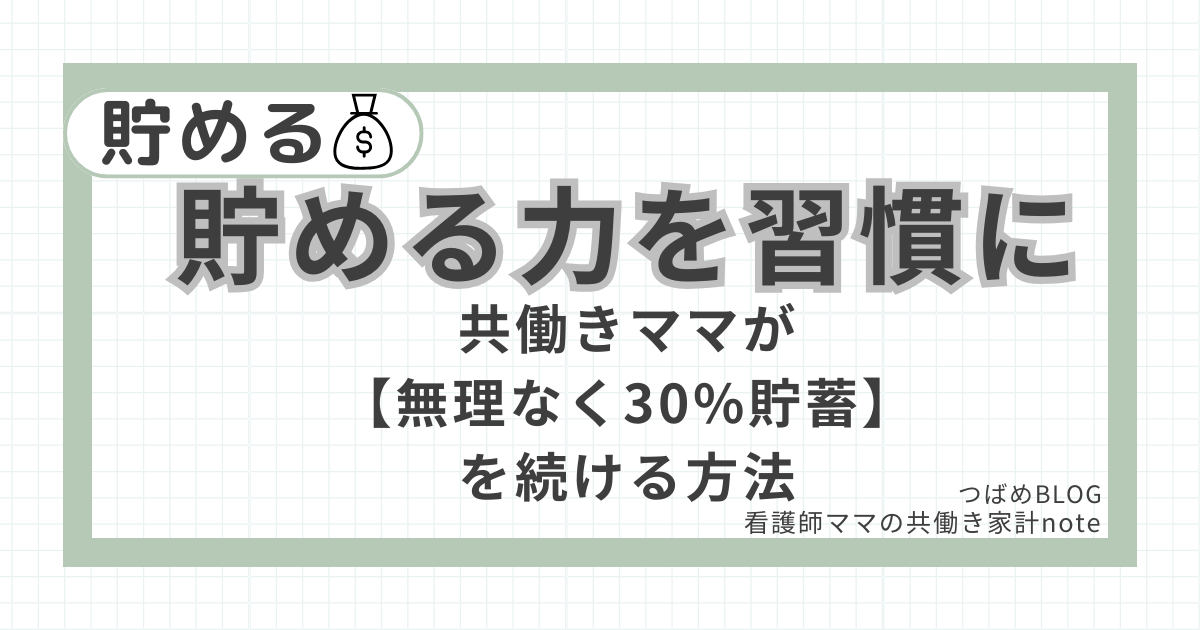
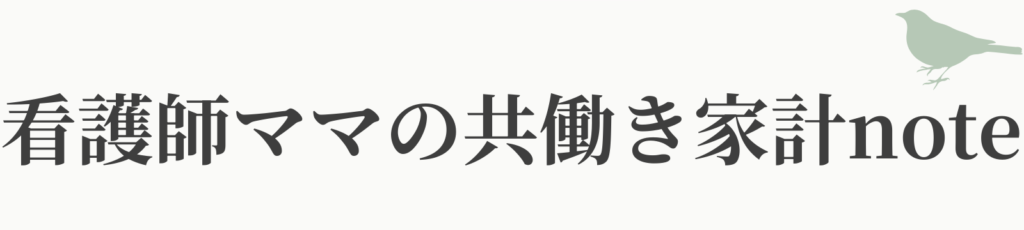

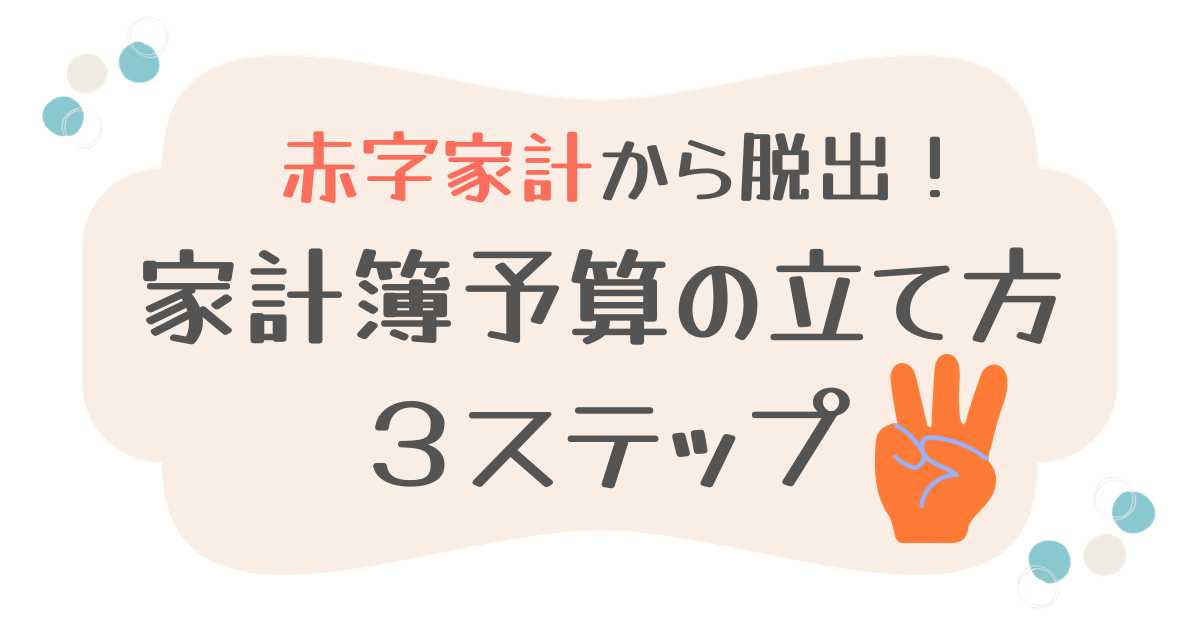

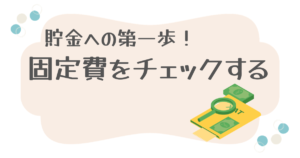
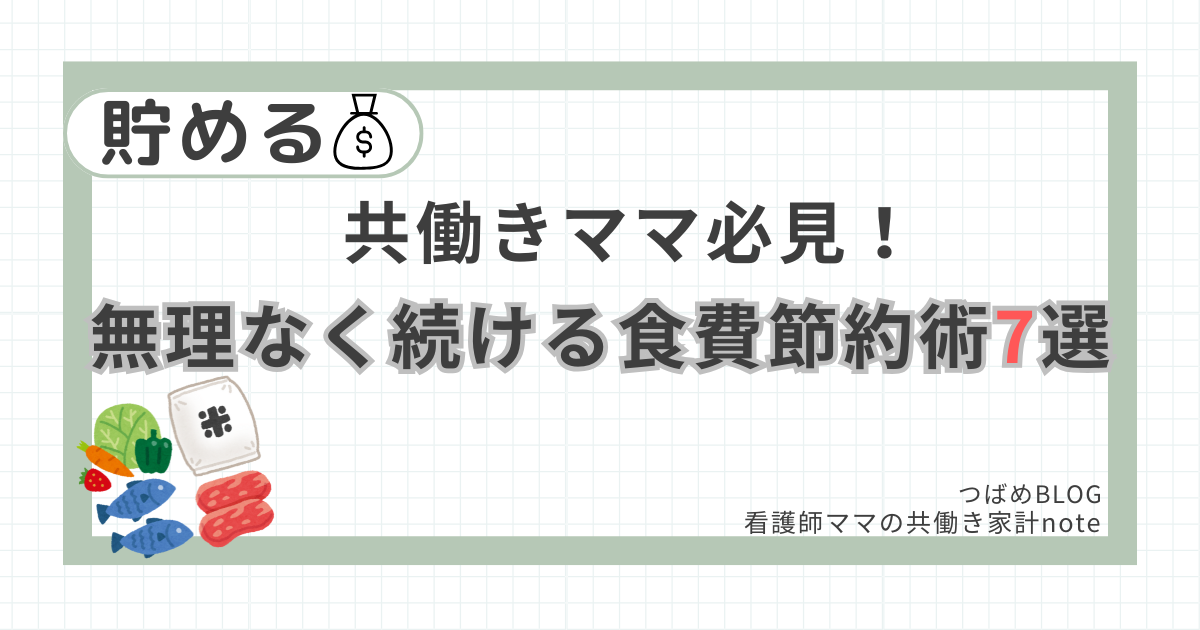
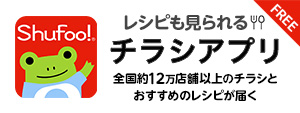
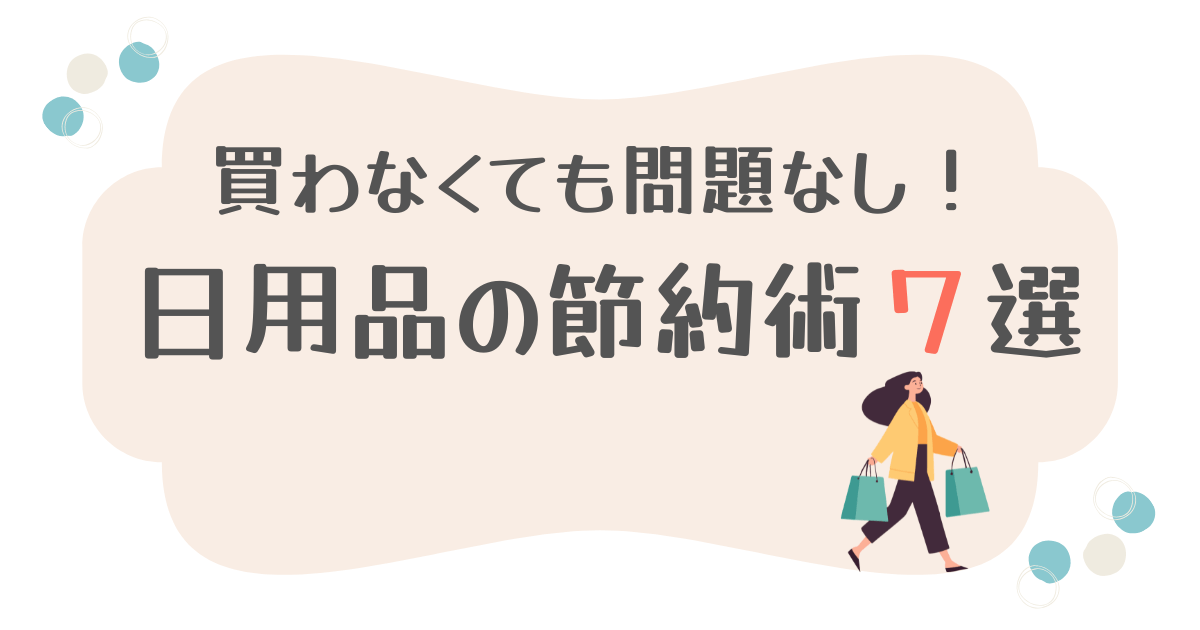

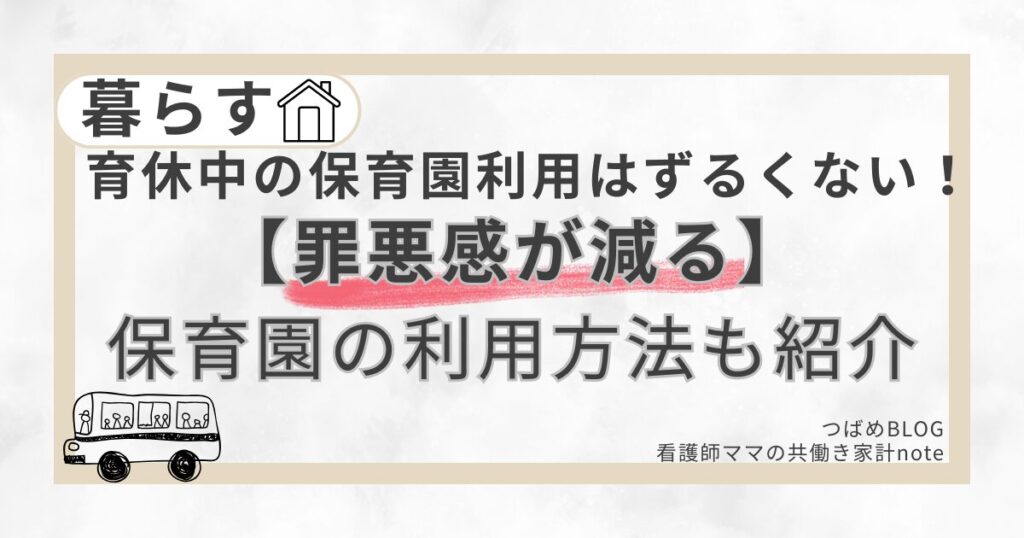



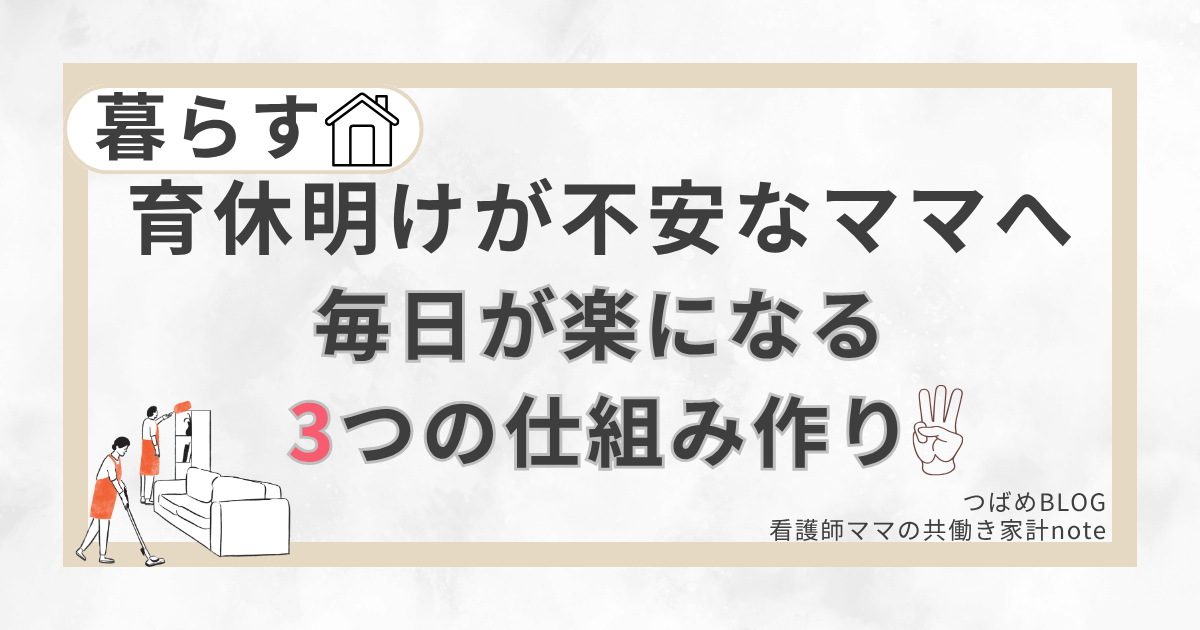
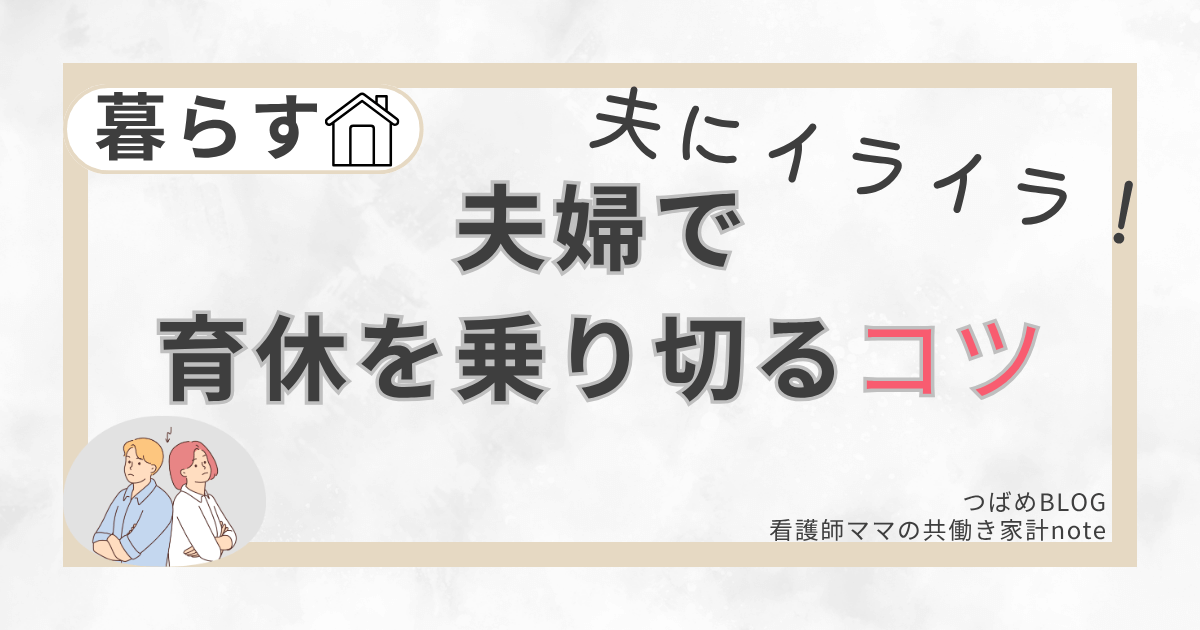
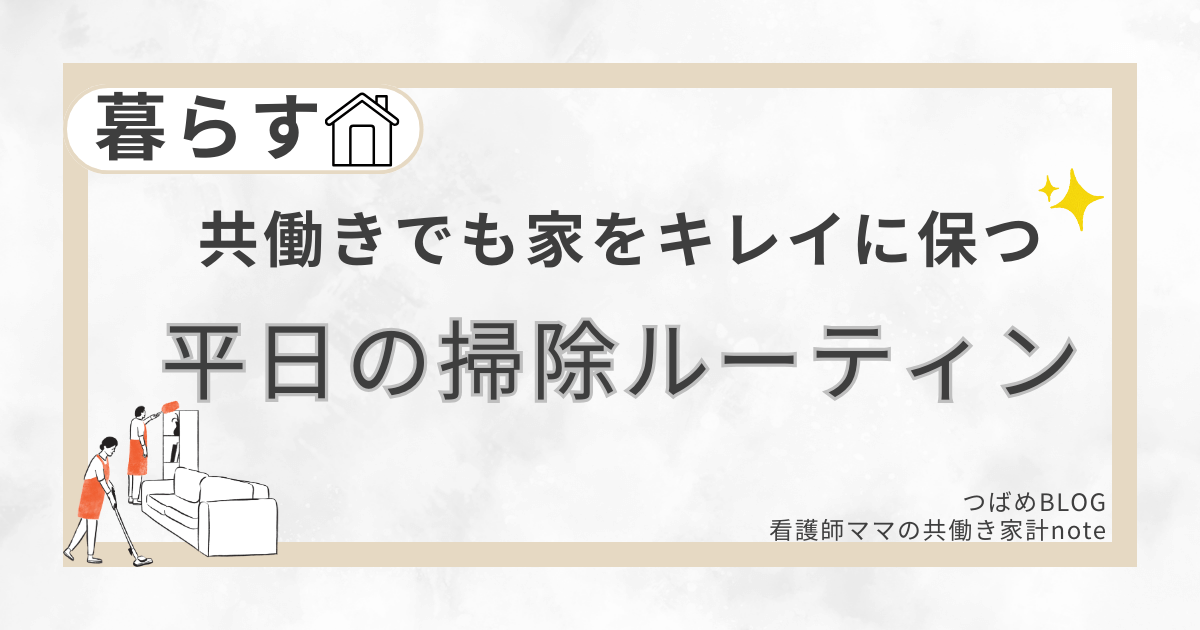
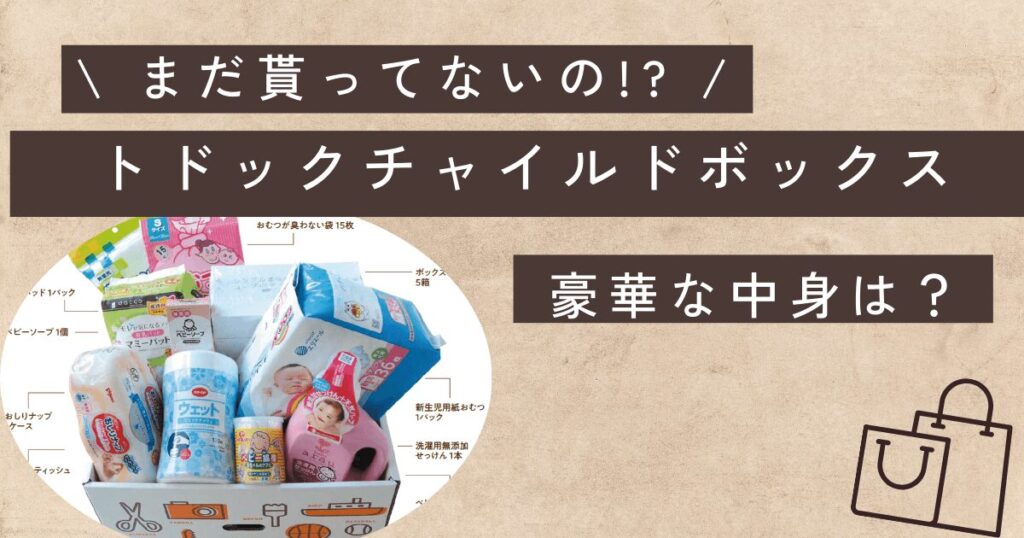
コメント